
離乳食を食べてくれない問題
離乳食を食べてくれない問題は、多くのお母さんが抱える問題ではないでしょうか。
娘も全然進まず、焦りましたので、小児科で行っている離乳食相談会に行ってきて、聞いたお話と、保育士さんのお話をご紹介したいと思います。
離乳食相談会で管理栄養士さんに相談
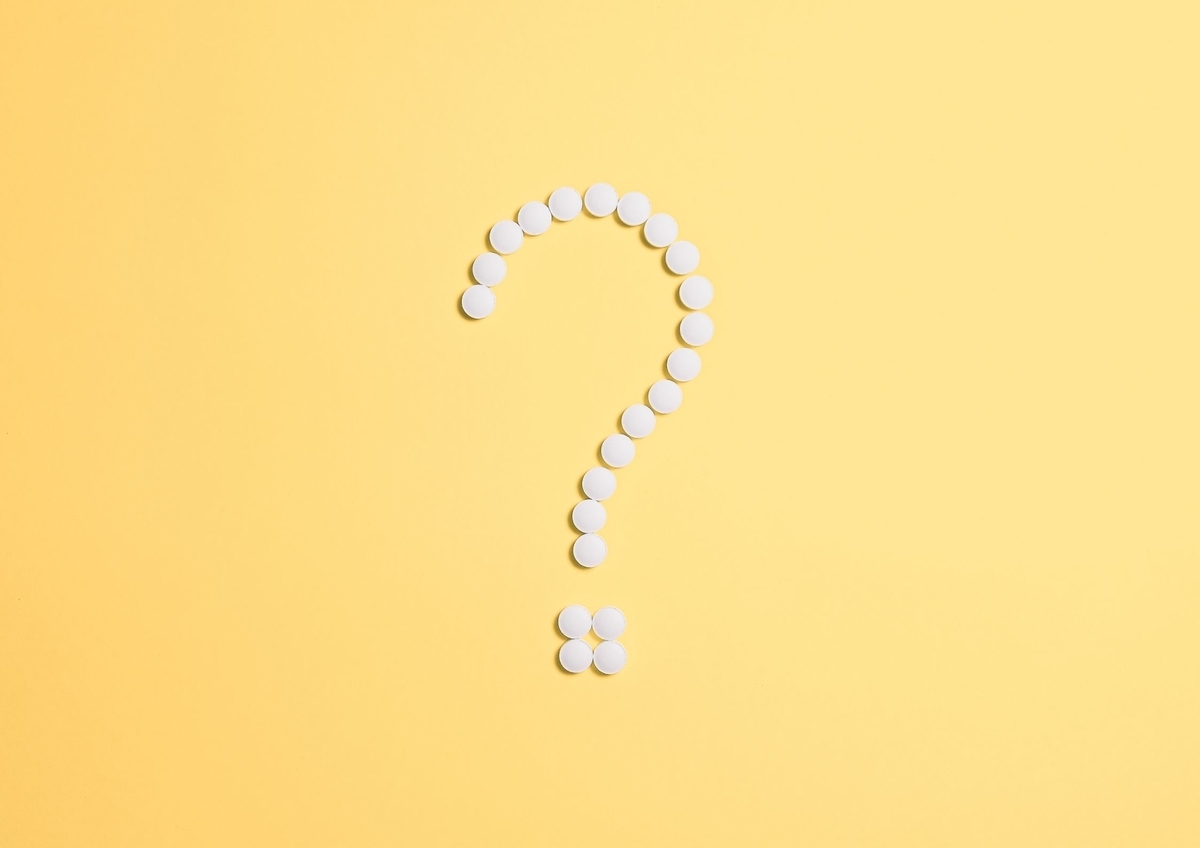
質問内容
Q. (ズバリ!)離乳食を食べてくれません。食べてくれる方法が知りたいです。
管理栄養士さんの回答
以下、管理栄養士さんからの4つのアドバイスです。
- 「何で苦手なのかをつきとめて、好きな食べ物を探しましょう!」
→ 好きなものを探せたら、食べることが嫌でなくなるのでいいですよね!
(しかし、うちの娘は、何をあげても拒否しました・・)
- お菓子をあげて、食べること自体にに慣れさせましょう!
→ お菓子が好きだったら、食べる練習になりますね。
(しかし、うちの娘は、お菓子も拒否しました・・)
- お菓子の先に離乳食をつけてみましょう!
→ お菓子を食べる赤ちゃんには良いかもしれません!
(お菓子も食べなかったので・・)
- スプーンを持たせながら食べさては?
→ 早くからスプーンを自分で持ちたい赤ちゃんもいるそうです!
残念ながら、娘には全て効きませんでした。

のけぞるのけぞる!!(すごい写真・・)
元ベテラン保育士の叔母のやり方

転機が訪れたのは、実家に帰省した時のこと。
保育士だった叔母が、
「私が食べさせてみる!食べさせる自信がある!」
と言ってくれ、娘に離乳食をあげてくれた時です。
私は内心、「いやいや、無理だよ・・」と思っていました。
ベテラン保育士の行動
自信満々に以下の行動を始めました。
- まず、皆がいるところから、二人きりになれるところに移動しました。
- そして、抱っこしてルンルンに踊りながら、「えらいね」「えらいね」とひたすら褒め始めました。
- スプーンをつけただけで「えらいね!」口を開けただけで「えらいね!」・・!!
- とにかく気分を良くすることに徹し、自分も食べるふりをして「美味しいー!!」
- テンションMAX
そして娘は、すりおろしリンゴを食べた。
それまで、一口も食べないか、一口食べてイヤな顔をしていた娘が食べ始め、私は目から鱗でした。
親の基本姿勢
あとで話を聞くと、簡単に思えますが、「楽しく」が基本とのこと。
「心は通じるから、食べないだろうと思っていたら食べない。絶対に食べると思ってあげること。」
言葉は分からなくても、「きっと食べないよー」、「離乳食あまり好きじゃないもんねー」「今日は食べてくれるかなー?」という雰囲気は、赤ちゃんに伝わっている。
とのこと。
私は、とても単純なことに思えて、その単純なことが出来ていなかったのです。
それからは、「たくさん食べさせること」よりも、「食べることを好きにさせてあげること」を、目標に置いて接するようになりました。
実際、好き嫌いの原因の一つは、「その食べ物に関するイヤな経験があったから」という見解もあります。
一口食べてくれたら、全力で褒める。
うちの娘の場合、結局は、気分とモチベーションだったのかもしれません!
10ヶ月の娘はその後、ギャル曽根というあだ名がつけられるくらい、もりもりご飯を食べてくれる子になりました。